「SWOT」とは?
みなさん、こんにちは。
今回は企業やプロジェクトの戦略立案に欠かせないフレームワークである「SWOT」について、基礎から実践的な応用までをじっくり解説します。
この動画を最後までご覧いただくことで、SWOTを用いた分析手法をマスターし、具体的にマーケティング活動にどう活かせるかが理解できるようになります。
それでは早速、入りましょう。
SWOTの概要と歴史的背景

ここではまず、SWOTとは何かという基礎知識をおさらいします。
SWOTとは、内部環境の強みと弱み、外部環境の機会と脅威を整理し、自社や自社製品が置かれている状況を総合的に把握するためのフレームワークです。
日本国内では経営戦略やマーケティング戦略の教科書的手法として広く知られており、数多くの企業が意思決定の土台として活用しています。
この手法はもともとアメリカの経営コンサルタントらが1960年代後半に開発したと言われており、以来世界中のビジネスパーソンに支持され続けてきました。
SWOTの名前は、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取ったもので、これら四つの視点を組み合わせることで意思決定のヒントを導き出します。
例えば、ある製品の強みを生かして、市場の機会を捉えるための戦略を立てる。こうした関係を明らかにすることで、企業は限られたリソースを最適に配分しやすくなります。
内部環境の構造理解:強みと弱み

SWOTの前半にあたるInternal factors、つまり企業やプロジェクト内部の要素には、StrengthとWeaknessがあります。
ここではまずStrength、つまり自社が競合他社よりも秀でている部分を掘り下げます。
具体的には製品の品質、技術力、ブランド認知度、人的資源、コスト競争力、チャネル網などが考えられます。
これらの要素は企業のコアコンピタンスであり、競争優位性を支える根幹です。
次にWeakness、すなわち自社内における改善点や競争上の課題です。
ここでは組織体制の硬直性、財務基盤の脆弱さ、新技術への遅れ、ブランド力不足、顧客サポート体制の不十分さなど、内側に秘められた弱みを洗い出します。
外部環境の構造理解:機会と脅威

続いてExternal factorsにあたるOpportunityとThreatを掘り下げます。
Opportunityは外部環境の変化によって生まれる新たなビジネスチャンスのことです。
社会トレンドの変化、技術革新、市場規模の拡大、規制緩和、提携機会など、企業が積極的に取り込みたい要素を指します。
一方、Threatは外部環境から受けるリスクや妨害要因を指します。
景気後退、競合激化、技術革新のスピード、新規参入、規制強化など、企業の成長を阻む可能性のある要素です。
脅威を正確に評価しないまま戦略を立てると、想定外のトラブルに直面した際に対応が遅れ、損失が拡大しかねません。
SWOTの組み合わせによる戦略立案

内部要因と外部要因を整理したら、いよいよクロス分析に進みます。
まずStrengthとOpportunityを組み合わせることで、積極的に攻める「SO戦略」を描きます。
強みを最大限に活かし、市場の機会を取り込むことで成長ドライバーを開拓します。
例えば、高い技術力を持つ企業が新興市場のニーズを掘り起こし、独自製品を投入してシェアを拡大するケースなどが該当します。
次にStrengthとThreatを組み合わせた「ST戦略」です。
強みを盾に外部の脅威から自社を守る、いわゆる防御策を策定します。
ブランド力が高い企業が価格競争の激化に直面した際、品質訴求型のポジショニングを強化する例がこれに当たります。
WeaknessとOpportunityを組み合わせる「WO戦略」は、内部の弱みを克服しながら新たな機会をつかむ戦略です。
例えば、マーケティング体制が未整備だった企業が、デジタル化の波に乗りオンライン広告を導入して集客ルートを多角化する、といったアプローチです。
最後にWeaknessとThreatを組み合わせた「WT戦略」は、最もリスクヘッジが求められる領域です。
内部の弱みが露呈しやすく、外部の脅威が顕在化すると経営危機に直結しかねません。
不要資産の売却、事業撤退、M&Aによる補強など、損失最小化を目的とした対策を講じます。
マーケティング活動への応用
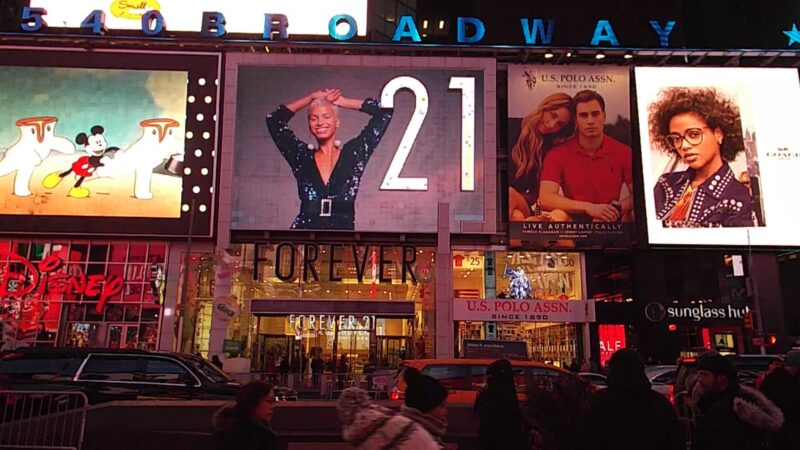
ではここから、SWOTを具体的にマーケティング活動にどう適用するかを議論します。
まずマーケティング戦略設計の初期段階でSWOTを実践することで、ターゲット市場の選定やポジショニング構築に大きな手がかりが生まれます。
Strengthを基盤にした差別化要因を明確にし、Opportunityが示す成長領域へリソースを振り向ける。
これによって一過性ではない、自社独自の優位性を持つ戦略を策定可能です。
次にプロダクトマーケティングにおいては、SWOTから抽出された内部・外部要素をもとに製品コンセプトを磨き込みます。
たとえば利用者のニーズを反映した機能開発に強みを集中投資し、同時に競合製品との差別化ポイントを明確化します。
また外部の機会として捉えた市場トレンドを製品改良に反映させることで、他社よりも一歩先を行くアドバンテージを築き上げられます。
さらにプロモーション活動にも応用が可能です。
広告コミュニケーションのメッセージ設計では、Strengthをベースにしたブランドストーリーを打ち出し、Opportunityが示す消費者心理に響くクリエイティブを開発します。
Threatに関しては、クライシスコミュニケーションプランとして危機時対応フローを事前に整備し、リスクを最小化しながらマーケティング活動を継続できる体制を構築します。
チャネル戦略においては、自社の流通網というStrengthを活かしつつ、新たな販路としてOpportunityに分類されるオンラインチャネルやOMO(Online Merges with Offline)の取り組みを拡大します。
これにより、従来の顧客層だけでなく新興顧客へのリーチが飛躍的に向上します。
事例

ここで国内外の例をもとに、SWOTがどのように役立ったかを解説します。
ある大手飲料メーカーは、独自の研究開発体制というStrengthを背景に、健康志向の高まりというOpportunityを的確に捉え機能性ドリンク市場へ参入しました。
同時に他社の新規参入というThreatを想定し、大々的なコミュニケーション投資を行うことでブランド認知を短期間で向上させ、競争優位を確立しました。
加えて、製造コストの高止まりというWeaknessを海外生産拠点の統廃合により解消し、収益性の改善にも成功しています。
実践ワークとまとめ

最後に、視聴者の皆さんに向けた実践ワークをご提案します。
自社や担当製品に関して、まずStrengthとWeaknessを洗い出し、その後OpportunityとThreatをリサーチしましょう。
一次情報だけでなく統計データや業界レポート、SNSの声といった二次情報も積極的に活用することで、より精度の高いSWOTが完成します。
その結果をもとに、4つの戦略タイプから自社に最適なものを検討し、次回のマーケティングミーティングでチームと共有してください。
本動画ではSWOTの基本からマーケティングへの応用事例、さらには実践ワークまでをカバーしました。
SWOTを継続的に活用することで、自社の現状を常に把握し、環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織力を養えます。
ぜひ今日からトライしてみてください。
それでは、今回の動画が役に立ったと感じたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました!
この記事は、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際 パブリック・ライセンスのもとで公表されたウィキペディアの項目「SWOT analysis」を素材として二次利用しています。


